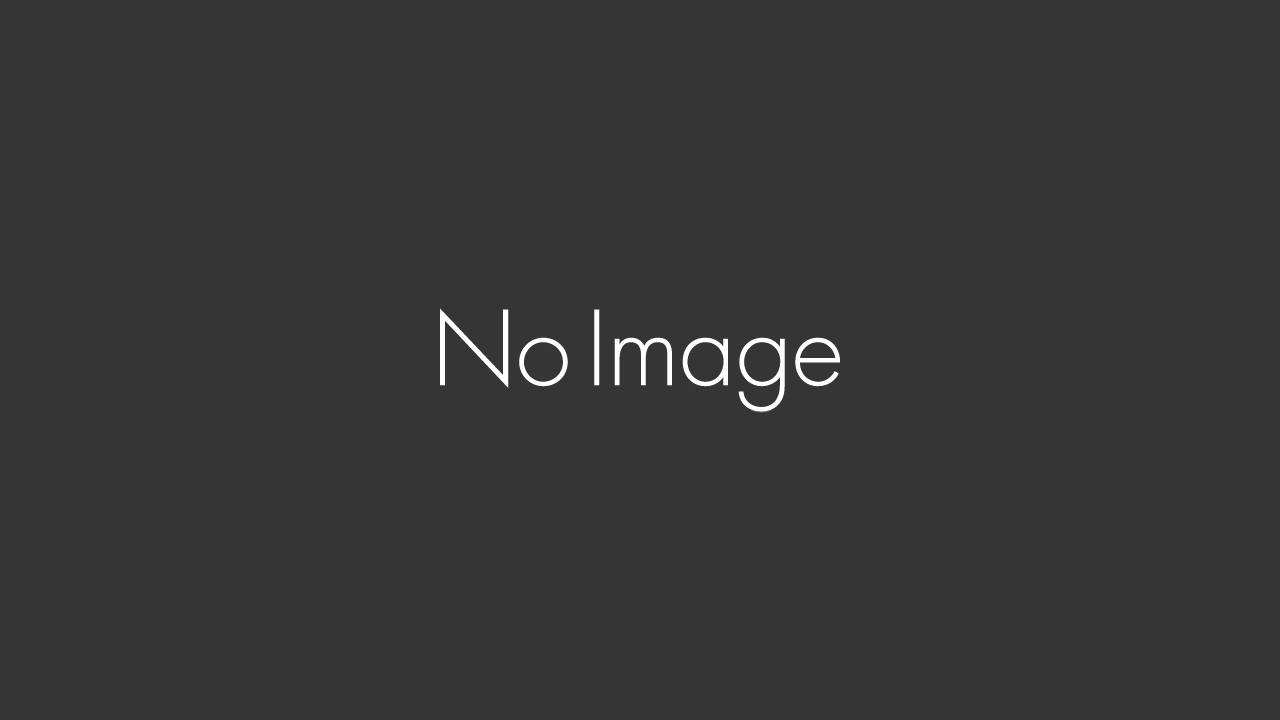今回は、京都は北白川『八大神社』のご紹介です。
この神社の特徴はずばり、宮本武蔵。
いやわかんねぇよ(゚Д゚)ハァ?q
実は僕も参拝するまでは宮本武蔵との縁は勿論、かろうじて名前知っている程度やったんが正直なところなんですが、それだけに見つけた穴場スポット(あくまで僕にとってですが)は嬉しい発見でした。では、今回はそんな宮本武蔵所縁の地『八大神社』に一礼。

ご本殿まで
京都市は左京区北白川、日本で(多分)二番目の学府、京都大学の北側に今回の八大神社はあります。この一帯は、知名度としてはそこまで高くないものの、自社・仏閣が点在している地域で、時間をかけて回りたいところです。
入口の鳥居と御由緒書き。


境内はさほど広くはありませんので、さくっとご参拝が可能です。



ご本殿。

本殿の手前には立砂もありました。

境内散策・御朱印
宮本武蔵像
本殿左には、宮本武蔵の像が鎮座します。

縁があるとするのは、この神社、ご祭神が宮本武蔵とかそういう訳ではありません。その昔、この神社の近所の一条寺下がり松で宮本武蔵は吉岡一門との決闘に挑んだそうで、その時決闘前にこの八大神社の前を通った宮本武蔵は、必勝祈願をしようとしたけど、途中で祈る事を辞めそのまま決闘に挑みそして勝利したという逸話に基づくものだそうです。
尊んでも、神仏に恃(たの)まず


これが、この時に悟った宮本武蔵の生きざまを示す一文と言われています。吉岡『一門』というからには相手は当然一人でなく、わらわらと一門衆総出でかかってくる事を考えると、如何に剣聖宮本武蔵と言えど決死の覚悟、この神社へ祈ろうという気持ちは神仏にすがる思いだったろうと思料します。
そこで宮本武蔵はむしろその神仏にすがろうとする気持ちを弱さ=恃む(あてにする)と捉え、弱さを断ち切ろうとしたんだと僕は考えました。昔はヒーローインタビューみたいなものはなかったでしょうから、本当のところはわからないですが。
初代下がり松

宮本武蔵が決闘した場所の目印『一条寺下がり松』ですが、現在はもう枯れてしまったらしく、宮本武蔵像の隣に展示されていました。木としての寿命は全うしたようですが、歴史の1ページを見た証人としての役割を今でも果たしているようです。
尚、元々この松が立っていたところには石碑が建てられています。


摂社:皇大神宮社
本殿右側にある摂社。


摂社:常盤稲荷
境内最奥にある石段の上にある摂社、常盤稲荷。



授与品と御朱印
社務所もやはり宮本武蔵がいっぱい。中でも宮本武蔵の決闘勝利にちなんだ勝利祈願のお守りが目につきました。

御朱印帳も豊富。この神社の大祭で使われる剣鉾差(けんほこさし)を描いたものと、宮本武蔵を描いたもの各2種。今回は御朱印帳の切れ目が来ていたので購入しました。

御朱印、いうまでもないですね、宮本武蔵が描かれています。

御由緒・ご利益
この神社の創建は1294年、以来京都一条寺の氏神様として信仰を集めてきました。
御祭神は以下3神。
素戔嗚命(すさのおのみこと)
稲田姫命(いなだひめのみこと)
八王子命(はちおうじのみこと)
ご利益は素戔嗚命と稲田姫命が夫婦神の為、2神にちなんだ縁結び、また、一条寺は今日の都の北東部にあたり、都の鬼門守護という位置づけから方除守護、他禊払い、農耕、森林・山、学業と、生活に密着したご利益が中心なのが特徴的。
ちなみにこの神社のご神紋は三つ巴紋と桔梗紋の二つのようです。

アクセスその他
- 住 所:〒606-8156 京都府京都市左京区一乗寺松原町1
- 駐車場:なし
電車の場合:叡山電鉄から東へ徒歩15分。
車の場合:北白川通りから曼殊院通りを東へ。
付近には有料駐車場あり。(定額500円)
まとめ
今回はこれで以上です。
近隣には曹洞宗の詩仙堂、圓光寺など時間をかけて拝観したい場所が多いです。また、個人的には一条寺は今やラーメン屋の聖地ともいうべき密集地、午前中にみっちりと観光で汗を流しお腹を空かせて、がっつりとラーメンを食すというのが個人的なお勧めの立ち回り方です。