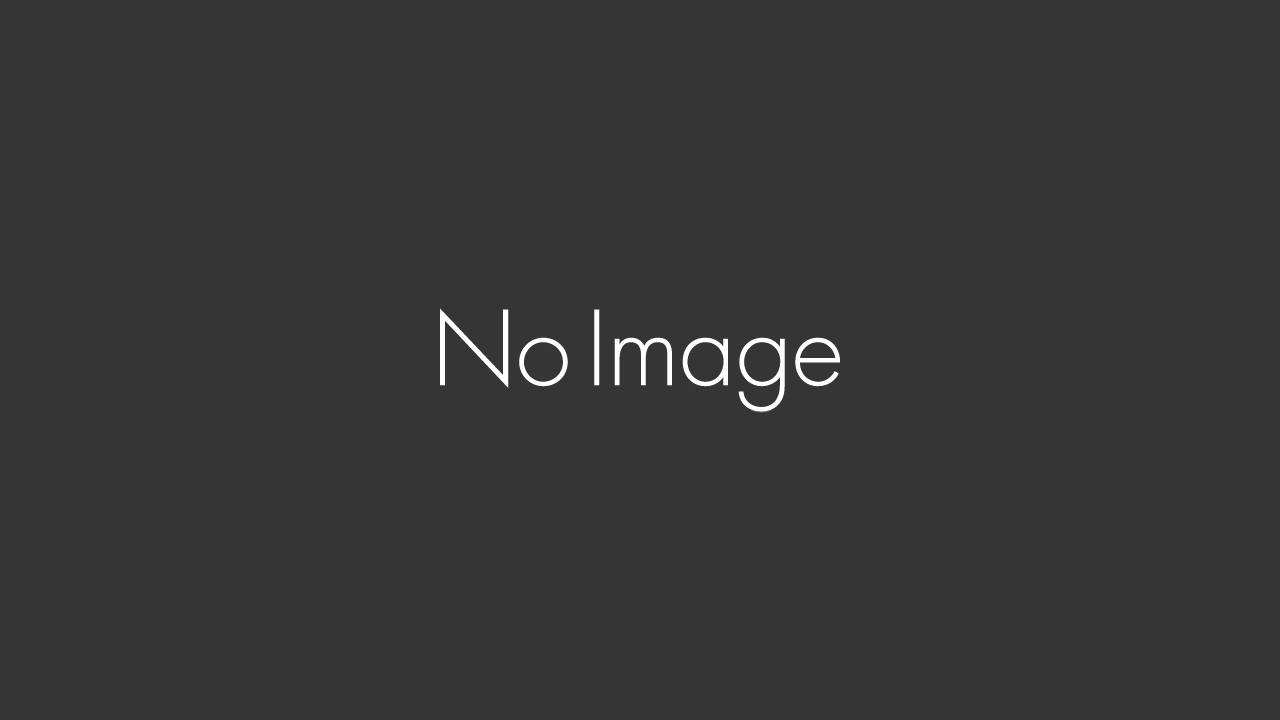宇治と言えば、平等院。何やかんや言いながら宇治を代表する観光スポットと言えます。
という方がいらっしゃれば、10円玉の表をご覧下さい。

この日本人なら誰もが幾度となく見たことがあって、何となく知ってるけどもしかしたら気にもしたことがない、そんな建物が今回ご紹介する平等院です。
では今回は、1994年の世界遺産登録以来、俄然日本人も外国人も絶賛急増中の平等院へ一礼。
10円玉の図柄
平等院と言えば、やはりこのショットです。

ちょっとずれたけど、10円玉の絵そのままというのは感じて頂けるかと思います。
観光客でごった返しているので、ベストショットをゆっくりという訳にもいかないんですが、季節・天気・時間などが合えば、水面に鏡面写しの建物と2面に撮る事が可能です。

これは院の裏側を撮った画像です、こんな風に綺麗に建物が鏡面に写したように見ることが出来る様はちょっと他に代えがたいものがあります。
拝観料・拝観時間
拝観料・拝観時間は以下の通り。(平等院公式HPより抜粋)


鳳翔館というのは、平等院宝物などの展示が楽しめる博物館です。
入口から境内散策
京阪でもJRでも宇治駅から10分程度、数多のお茶屋さんと甘味屋さんが軒を連ねる平等院通りに出ます。

通りには誘惑も多いんですがひとまず置いといて、通りを抜ければ一際目立つ石碑が、平等院前庭。よく手入れされた前庭を抜けると見えてくる入口の門、ここが平等院の入口です(正確には表参道入口です。)

前庭も境内もよく手入れが行き届いた綺麗なお庭を愛でることが出来ます。
平等院の看板:藤棚
入口から抜けると、まず出迎えてくれるのが、平等院の名物の一つ『藤棚』です。季節柄今は霧吹機が設置された休憩スポットになっていますが、季節なら見事に下がる藤の花が棚一杯に広がる圧巻の光景はインスタ映え抜群です。

10円玉の表:鳳凰堂
藤棚を横目に広がる池、その池を挟んで向かい側に立つのが、院のメイン『鳳凰堂』、国宝・世界遺産です。

真ん中が本堂の阿弥陀堂で、左右にもお堂を備えその両脇が翼のように広がっている様が鳥が羽を広げているかのような姿に見える事と、屋根の上に一対の鳳凰を備えている事が『鳳凰堂』と呼ばれる所以です。


今の鳳凰は陽光を照り返して煌びやかに輝く金色ですが、昔の鳳凰は銅製やったらしく、今は青銅色が歴史を偲ばせる姿で鳳翔館に展示されています。
また、平等院は日本のお金に縁のあるらしく、一万円札に描かれている鳥がこの鳳凰との事です。意識するのは福沢諭吉の方で、どうしても意識してみる機会はないかもしれませんが、間近でご覧になれば合点がいくはず。(流石に展示の前で一万円札拡げて見比べてる人はいなかったですが)
夏は百日紅
平等院は春から秋にかけて、桜、藤、百日紅、紅葉と季節それぞれに美しい姿を拝むことが出来ますが、夏はこの百日紅が楽しめます。
藤や桜に比べると知名度は下がりますが、特にこの正面左に咲く百日紅と朱のお堂のグラデーションは一見の価値ありです。



御朱印は2種類:集印所
表参道入口から向かって一番奥側に集印所が設けられています。集印というのはあまり聞き覚えがないんですが、内容は御朱印所と受取ってもらって差し支えありません。


頂ける御朱印は二種。鳳凰堂と阿弥陀如来。この平等院は、鳳凰堂に鎮座する阿弥陀如来坐像も国宝・世界遺産登録がなされている為でしょう。

今回は鳳凰堂の方を頂きました。

日本三名鐘の一つ
鳳凰堂の左側、百日紅の辺りにある石段の上に梵鐘が配置されています。今の梵鐘は2代目だそうですが、日本三名鐘と呼ばれる一つです。初代梵鐘も鳳翔館に展示されています。

鳳翔館
先ほどよりちょいちょい登場する鳳翔館ですが、平等院内の数多くの国宝を永く保存する為に2013年に建てられたミュージアムです。宗教法人としてはかなり珍しいんだとか。初代の梵鐘や鳳凰、雲中供養菩薩像など、多くの国宝をガラス越しながら間近で拝むことが出来ます。博物館ながら、魅せるというところにこだわりを感じる内容になっていて、さながら美術館のようです。入館料は院の拝観料に込みなっています。
浄土院・羅漢堂
鳳凰堂の丁度裏手にあるのがこの浄土院と羅漢堂です。




15世紀半ばごろ栄久上人が平等院修復の為に開創したというお堂です。というのも、平等院は南北朝時代、楠木正成が火を放ち燃やしてしまったんだそうです、今から振り返れば何ちゅうことすんねん!以外何でもないですが、平等院をというより、先に布陣した正成は相手に戦略拠点を築かせないために辺り一面を焼き払ったそうです。で、その平等院を復活させよう、としたのがこの栄久上人という訳です。
つまり今、この昔の姿が復元されているのはこの栄久上人のお陰。
ここでも百日紅を鑑賞することが出来ます。


源頼政公墓所
不動堂、景勝院と共に立つのが、平等院で自害した源氏の武士のお墓です。


源氏姓ながら、義朝に見切りをつけ平氏家臣として与した武士です。平清盛の元で武士の世を築く重要な役割を担う者として期待されていたんですが、当時は源氏に完全勝利した平家、やりたい放題やったのを見かね以仁王に呼応して挙兵するも、勢いある平家に追い詰められ、この地で果てたという中々数奇な運命を辿った武将です。
歴史・由緒
1053年藤原頼通によって建立されました。摂関政治のピークが藤原道長と言われていますが、その長男です。正に藤原摂関家全盛期の申し子と言える方です。
その後、以仁王に呼応した源頼政が平家打倒に挙兵するも敗北、この平等院で自害したとされています。以来、切腹の元祖と言われていて、『切腹』とは武士にとって自らで幕引きする誉と扱われるようになったそうです。
1300年くらいに楠木正成がこの辺り一帯に放火、奇跡的に焼け残った鳳凰堂以外の殆どが焦土と化します。
その後15世紀中ごろ平等院の修復に関する取組が行われ、その後幾度かの荒廃に見舞われながらも今日にその姿を残し続けているという訳です。
戦火や大火に見舞われ、幾度となく荒廃が進みながらもこうして今この姿が保たれているのは信心は勿論でしょうが、奇跡と言えるものでありそれ故に国宝として保護されるべき存在とされている由縁なのでしょう。
アクセス・その他
- 住 所:〒611-0021 京都府宇治市宇治蓮華116
- 駐車場:なし
電車の場合
京阪・JRとも宇治駅徒歩10分程度。京阪の場合、少し遠回りになりますが、駅を出て、川岸を上流に進み宇治神社・宇治上神社の参拝も一緒に考えるとトータルの時間は少なくまとまるかと思います。また、橋上からの景観も見ごたえがあり、春なら川中の塔の島の桜を鑑賞しながら向かう事も可能です。

車の場合
平等院の表参道である平等院通は車通行は道交法上可能なものの、実質は観光客がひしめき合う中抜ける上、そもそも駐車場自体(ほぼ?)ありません。なので、最寄のパーキングとしては、隣の縣通、もしくは二本隣りの宇治橋通商店街通に点在するコインパーキングを利用すればどこかに空きを見つける事は出来るかと思います。
①縣通
②宇治橋通商店街通
ただ、当然近隣は満車の率が高く、遠ければ徒歩の時間が増えるので、平等院通り巡りを考えると少し遠回りにはなりますが、裏門から道路を挟んで向かい側にある駐車場を利用するのが確実かもしれません。
まとめ
宇治で観光を考えるなら勧められるでもなくこの平等院は候補筆頭に挙げられるものかと思いますが、そのほかにも良い所は多いですし最近観光客増加に伴ってお土産屋さん、お茶屋さん、カフェ、ランチ、酒処と店舗は急増する傾向にあります。お勧めの店は色々とこのブログでもご紹介させて頂いておりますが、これからも色んなお店は増える事と思いますので、観光に来られた際は色んなお店巡りもきっと楽しんでもらえることと思います。
季節折々綺麗な姿を見せてくれますが、秋は絶景。特別拝観を実施しています。