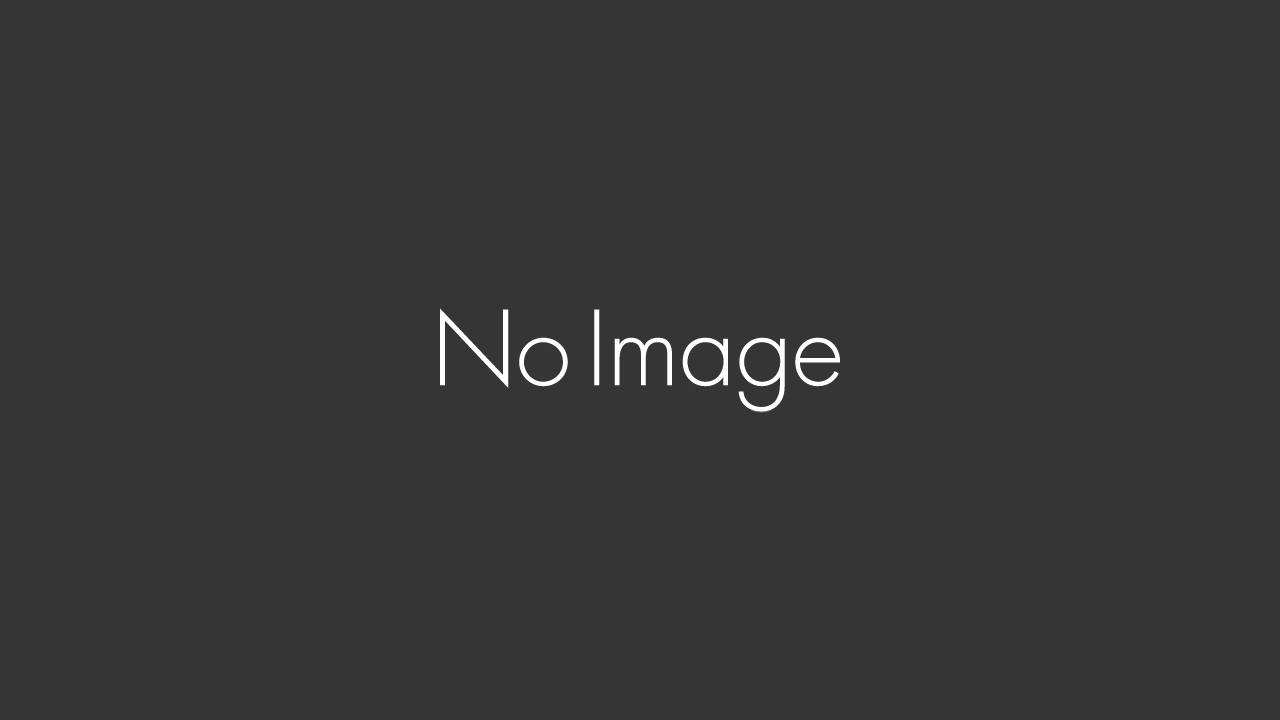節分の豆まきは誰もが一度はしたことがあるはず。
『鬼は外』の掛け声と一緒に鬼役(大体父親)に力の限り豆をぶつける厄除け祈願を行う家庭でもできる行事ですが、これを神事として行う神社があります。それが吉田神社です。
例年50万人が訪れ、境内には沢山の露店が軒を連ねごった返すのですが、普段は山裾にひっそりと佇む静かな神社です。
では、今回は吉田神社に一礼。

鳥居をくぐって、まず見えるのが向かって左の鳥居。末社、今宮社です。



今宮社を横目に石段を登ると、本宮に到達。
この吉田神社、山が約一つ分そのまま境内になっているようで、隅々まで参拝して回るとかなり大変w今回は特に夕方の参拝やったので、周れるだけ周る方向で計画。

本殿前の鳥居。


ご本宮。


本宮をうまいこと撮れるポイントがなかったんですが4社。
健御賀豆知命(たけみかづちのみこと)
伊波比主命(いはいぬしのみこと)
天之子八根命(あめのこやねのみこと)
比売神(ひめがみ)
ご利益(御神徳)は厄除・開運、学問、良縁・夫婦和合。
御由緒は、859年中納言『藤原山蔭』が京都の鎮守神として吉田山に勧請し創建されたのが始まりだそうです。そもそもこの吉田山は神楽岡と呼ばれ、読んで字の如く神が集いし岡として親しまれた聖地だったそうです。
次に御朱印を頂きに社務所へ。

拝殿には鬼の朱書きがされた割符がありました。開運守護の札だそうですが、漢字一文字も読めない子(5歳)が『何でも願いが叶う木のやつがあるで!!』と教えてくれた位なので、結構効果があるのかもしれません。

本宮横にあった酒殿。

本宮の手前には先の神楽岡信仰の証だろう摂社神楽岡社。一説に、本宮創建時には既に鎮座されていたという事なので、この地の祖の神様というべきお社ですね。

本宮鳥居前には若宮社へ続く石段があり

その石段横にはさざれ石、それに神鹿の像があります。


さざれ石は君が代に出てくる『さざれ石』との事で、さざれ石は雨が降るほどに大きな岩になるそうです、更に苔が生えるほどまで長く国家が続くようにとの意味が込められていて、国家繁栄の象徴なんだそうです。(初めて知ったのは内緒です。。)

神鹿は『鹿と言えば』の奈良県春日大社からの勧請のようですね。
本宮から裏側の道は二股に分かれ、一方の道は菓祖神社へ続きます。


『お菓子』の『祖』つまりお菓子の神社という一風変わった神社です。


ご祭神は
田道間守命
林浄因命
田道間守命は垂仁天皇の命により、常世の国に渡り不老不死の霊菓『非時香菓(現在の橘。みかんなどの総称)』を持ち帰った事に際し、お菓子の神様として信仰を集めるようになったとか。(今は菓子と果物は別物ですが、昔はひっくるめて『菓子』としていたようですね。)
もう一神の林浄因命は、1359年日本で初めて饅頭を作り、足利将軍家を通じ、宮中に献上するに至った方との事です。
今回はこれで以上です。豆まきの時期は勿論ですが、ゆっくりと境内を見て回るなら今の時期見て回るのも一興です。
- 住 所:〒606-8311 京都府京都市左京区吉田神楽岡町30
- 駐車場:あり